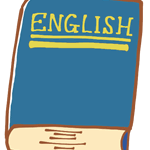技術翻訳の順序
技術翻訳は、一般的に、次のような順序で行います。
(1) 準備
翻訳原稿をざっと読み、概要を理解します。
翻訳原稿に参考資料が添付されている場合は、それを一通り読みます。
もし翻訳原稿を読んでもあまり理解できなかった場合は、自分で参考資料を入手して読みます。
次に、参考資料で使われている用語や、翻訳原稿に頻繁に出てくる用語を調べて、自前の対訳用語集にメモします。
パソコンを使う前は、この用語集として、私は紙のノートを使っていました。
パソコンを使うようになってからは、最初はPDICサービスを用語集として使っていました。しかし翻訳の用語は、同じ用語であっても発注者(執筆者)ごとにかなり異なり、また、慣用的な使用法があり、そうした個別の翻訳基準(翻訳仕様とも言います)を守る必要があります。そこで、翻訳用の私製の用語集は、発注者ごとや技術分野ごとに別々に分けた方が便利です。このような使い方にはPDICはあまり向きません。
そのため、私は、現在は、Microsoft Excelファイルに用語集を書き込んでいます。この方が、データのコピーや消去などのデータ管理が簡単ですので、より実用的だと思います。英和用語集はABC順に、和英用語集はあいうえお順に用語を配列して管理しています。
こうした翻訳前の準備段階で、かなりの時間が費やされます。
(2) 翻訳
いよいよ翻訳に取り掛かります。
翻訳された文章は、通常は、Microsoft Wordに書き込みますが、上書き翻訳と言って、Microsoft Word、Excel、PowerPointなどのファイルの翻訳該当箇所の原文を消して訳文を書き込む場合もあります。
翻訳は、原則として、文章(sentence)単位で行います。
といっても、たとえば、1つの英文を1つの和文に翻訳するとは限りません。1つの文章を2つ以上の文章に分けてから翻訳することはしばしばあります。逆に、2つ以上の文章を1つの文章にまとめてから翻訳することはほとんどありません。また、場合によっては文章の順序を変更することもあります。しかし、こうした文章の順序変更などが原因で、一部の文章をそっくり翻訳し忘れることもあります。そのような脱落を防ぐためには、翻訳後の仕上げ作業が重要になってきます。
私の場合は、原文を直接翻訳するのではなく、頭の中で一時的に明快な文章に書き直してから、それを翻訳するようにしています。どう訳してよいかわからない個所は、とりあえず空白にしておくか、あるいは、「?????」などの記号を付けておき、後から、その場所に戻って翻訳を補うようにしています。
訳語がわからない場合、当初はその都度専門用語辞典を用意して、言葉を調べていました。地元の図書館にはほとんど役に立つ辞書はありませんでしたので、書店まで出かけてゆき、自費で購入しました。1万円程度の仕事をするのに2~3千円程度の辞書を購入することもしばしばでした。購入した辞書の中には、ほとんど毎回、翻訳のたびに使った辞書もありましたが、購入後たったの1回しか使わなかった辞書の方が多かったと思います。
その後インターネットを使うようになってからは、たいていの用語はインターネットで調べることができるようになり、専門用語辞典を購入する機会は激減しました。インターネットでの辞書としては、スペースアルクとWeblio英和辞典・和英辞典が便利ですが、これらに載っていない専門用語はGoogleで調べられます。翻訳者にとって、現代はかなり快適な時代ではないでしょうか。
(3) 仕上げ
さて、翻訳が一通り終わった段階で、次に、翻訳された文章を、文章単位で、原文と訳文を対応させて見直します。訳文が意味不明瞭であったり、言葉として不自然な場合は、このステップを何回か繰りかえして改善します。実は、この見直しをしないで、翻訳した後、そのまま納品する方もごくわずかですがいるようです。
30数年前のことですが、ベテランのK氏は、300ページほどの取扱説明書の翻訳などを受注した場合、原稿を熟読後しばらく放置しておいて、頭の中で熟成させておき、締め切り近くになると一気に数日間で翻訳し、見直しはしないでそのまま納品している、とご自分で話されていました。そのような手順をとっていて、今まで問題があったことなかったということでした。取扱説明書は繰り返し同じ表現が出てくるので、一般に翻訳の効率は良いのですが、このような超高速翻訳は、天才的なK氏だから特別にできたことであったと思います。一般の翻訳者では不可能でしょう。もちろん、私にも不可能です。
上記の、原文と訳文を対応させての見直しが終了後、今度は、訳文のみを連続して読む見直しを行います。この時は、不自然な文章の流れや不明瞭な論理的展開をチェックし修正します。私の場合、この連続見直しは最低でも2回は行います。この連続見直しは、絶対に必要な作業であると思いますが、しかし、長い時間をかければかけるほど訳文が良くなるというわけではありません。
この後、Microsoft Wordなどの機能を使って、スペルチェックと文章チェックを行います。
最後に、段落単位で原文と訳文を照らし合わせて、脱落箇所がないかどうか調べます。かつて、1ページをそっくり脱落させてしまった翻訳者もいましたので、この脱落チェックはとても重要です。